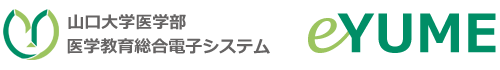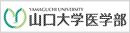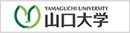検索
Search
- B 社会と医学・医療
- B-1 集団に対する医療
- B-1-1) 統計の基礎
- ①データの記述と要約(記述統計を含む)ができる。(B-1-1-*-1) [2]
- ②主要な確率分布を説明できる。(B-1-1-*-2) [2]
- ③正規分布の母平均の信頼区間を計算できる。(B-1-1-*-3) [2]
- ④基本的な仮説検定の構造を説明できる。(B-1-1-*-4) [2]
- B-1-2) 統計手法の適用
- ①2群間の平均値の差を検定できる(群間の対応のあり、なしを含む)。(B-1-2-*-1) [2]
- ②パラメトリック検定とノンパラメトリック検定の違いを説明できる。(B-1-2-*-2) [2]
- ③カイ2乗検定法を実施できる。(B-1-2-*-3) [2]
- ④一元配置分散分析を利用できる。(B-1-2-*-4) [2]
- ⑤2変量の散布図を描き、回帰と相関の違いを説明できる。(B-1-2-*-5) [2]
- ⑥線形重回帰分析、多重ロジスティック回帰分析と交絡調整を概説できる。(B-1-2-*-6) [2]
- B-1-3) 根拠に基づいた医療
- ①根拠に基づいた医療<EBM>の5つのステップを列挙できる。(B-1-3-*-1) [3]
- ②Patient, population, problem, intervention (exposure), comparison, outcome <PICO (PECO)>を用いた問題の定式化ができる。(B-1-3-*-2) [3]
- ③研究デザイン(観察研究(記述研究、横断研究、症例対照研究、コホート研究)、介入研究(臨床研究、ランダム化比較試験)、システマティックレビュー、メタ分析(メタアナリシス)を概説できる。(B-1-3-*-3) [2]
- ④データベースや二次文献からのエビデンス、診療ガイドラインを検索することができる。(B-1-3-*-4) [2]
- ⑤得られた情報の批判的吟味ができる。(B-1-3-*-5) [2]
- ⑥診療ガイドラインの種類と使用上の注意を列挙できる。(B-1-3-*-6) [2]
- ⑦診療ガイドラインの推奨の強さについて違いを説明できる。(B-1-3-*-7) [1]
- B-1-4) 疫学と予防医学
- ①人口統計(人口静態と人口動態)、疾病・障害の分類・統計(国際疾病分類(International Classification of Diseases <ICD>)等)を説明できる。(B-1-4-*-1) [4]
- ②平均寿命、健康寿命を説明できる。(B-1-4-*-2) [5]
- ③罹患率と発生割合の違いを説明できる。(B-1-4-*-3) [5]
- ④疫学とその応用(疫学の概念、疫学指標(リスク比、リスク差、オッズ比)とその比較(年齢調整率、標準化死亡比(standardized mortality ratio <SMR>))、バイアス、交絡)を説明できる。(B-1-4-*-4) [6]
- ⑤予防医学(一次、二次、三次予防)と健康保持増進(健康管理の概念・方法、健康診断・診査と事後指導)を概説できる。(B-1-4-*-5) [9]
- B-1-5) 生活習慣とリスク
- ①基本概念(国民健康づくり運動、生活習慣病とリスクファクター、健康寿命の延伸と生活の質(quality of life<QOL>)向上、行動変容、健康づくり支援のための環境整備等)を説明できる。(B-1-5-*-1) [7]
- ②栄養、食育、食生活を説明できる。(B-1-5-*-2) [5]
- ③身体活動、運動を説明できる。(B-1-5-*-3) [3]
- ④休養・心の健康(睡眠の質、不眠、ストレス対策、過重労働対策、自殺の予防)を説明できる。(B-1-5-*-4) [3]
- ⑤喫煙(状況、有害性、受動喫煙防止、禁煙支援)、飲酒(状況、有害性、アルコール依存症からの回復支援)を説明できる。(B-1-5-*-5) [5]
- ⑥ライフステージに応じた健康管理と環境・生活習慣改善(環境レベル、知識レベル、行動レベルと行動変容)を説明できる。(B-1-5-*-6) [7]
- B-1-6) 社会・環境と健康
- ①健康(健康の定義)、障害と疾病の概念と社会環境(機能障害、活動制限、参加制約、生活の質<QOL>、ノーマライゼーション、バリアフリー、ユニバーサルデザイン等)を説明できる。(B-1-6-*-1) [3]
- ②社会構造(家族、コミュニティ、地域社会、国際化)と健康・疾病との関係(健康の社会的決定要因(socialdeterminant of health))を概説できる。(B-1-6-*-2) [6]
- ③仕事と健康、環境と適応、生体環境系、病因と保健行動、環境基準と環境影響評価、公害と環境保全が健康と生活に与える影響を概説できる。(B-1-6-*-3) [5]
- ④各ライフステージの健康問題(母子保健、学校保健、産業保健、成人・高齢者保健)を説明できる。(B-1-6-*-4) [3]
- ⑤スポーツ医学を説明できる。(B-1-6-*-5) [1]
- B-1-7) 地域医療・地域保健
- ①地域社会(へき地・離島を含む)における医療の状況、医師の偏在(地域、診療科及び臨床・非臨床)の現状を概説できる。(B-1-7-*-1) [5]
- ②医療計画(医療圏、基準病床数、地域医療支援病院、病診連携、病病連携、病院・診療所・薬局の連携等)及び地域医療構想を説明できる。(B-1-7-*-2) [4]
- ③地域包括ケアシステムの概念を理解し、地域における、保健(母子保健、学校保健、成人・高齢者保健、地域保健、精神保健)・医療・福祉・介護の分野間及び多職種間(行政を含む)の連携の必要性を説明できる。(B-1-7-*-3) [8]
- ④かかりつけ医等の役割や地域医療の基盤となるプライマリ・ケアの必要性を理解し、実践に必要な能力を獲得する。(B-1-7-*-4) [4]
- ⑤地域における救急医療、在宅医療及び離島・へき地医療の体制を説明できる。(B-1-7-*-5) [7]
- ⑥災害医療(災害時保健医療、医療救護班、災害派遣医療チーム<DMAT>、災害派遣精神医療チーム<DPAT>、日本医師会災害医療チーム<JMAT>、災害拠点病院、トリアージ等)を説明できる。(B-1-7-*-6) [3]
- ⑦地域医療に積極的に参加・貢献する。(B-1-7-*-7) [4]
- B-1-8) 保健・医療・福祉・介護の制度
- ①日本における社会保障制度と医療経済(国民医療費の収支と将来予測)を説明できる。(B-1-8-*-1) [4]
- ②医療保険、介護保険及び公費医療を説明できる。(B-1-8-*-2) [3]
- ③高齢者福祉と高齢者医療の特徴を説明できる。(B-1-8-*-3) [3]
- ④産業保健(労働基準法等の労働関係法規を含む)を概説できる。(B-1-8-*-4) [3]
- ⑤医療の質の確保(病院機能評価、国際標準化機構(International Organization for Standardization <ISO>)、医療の質に関する評価指標、患者満足度、患者説明文書、同意書、同意撤回書、クリニカルパス等)を説明できる。(B-1-8-*-5) [6]
- ⑥医師法、医療法等の医療関連法規を概説できる。(B-1-8-*-6) [4]
- ⑦医療関連法規に定められた医師の義務を列挙できる。(B-1-8-*-7) [6]
- ⑧医療における費用対効果分析を説明できる。(B-1-8-*-8) [3]
- ⑨医療資源と医療サービスの価格形成を説明できる。診療報酬制度を説明でき、同制度に基づいた診療計画を立てることができる。(B-1-8-*-9) [4]
- ⑩医療従事者の資格免許、現状と業務範囲、職種間連携を説明できる。(B-1-8-*-10) [9]
- ⑪感染症法・食品衛生法の概要と届出義務を説明できる。(B-1-8-*-11) [3]
- ⑫予防接種の意義と現状を説明できる。(B-1-8-*-12) [2]
- ⑬障害者福祉・精神保健医療福祉の現状と制度を説明できる。(B-1-8-*-13) [2]
- B-1-9) 国際保健
- ①世界の保健・医療問題(母子保健、感染症、非感染性疾患(non-communicable diseases <NCD>) 、UHC (UniversalHealth Coverage)、保健システム(医療制度)、保健関連SDG (Sustainable Development Goals))を概説できる。(B-1-9-*-1) [2]
- ②国際保健・医療協力(国際連合(United Nations <UN>)、世界保健機関(World Health Organization <WHO>)、国際労働機関(International Labour Organization <ILO>)、国連合同エイズ計画(The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS <UNAIDS>)、世界エイズ・結核・マラリア対策基金(The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria <GF>)、GAVI アライアンス(The Global Alliance for Vaccines and Immunization <GAVI>) 、国際協力機構(Japan International Cooperation Agency <JICA>) 、政府開発援助(Official Development Assistance <ODA>)、非政府組織(Non-Governmental Organization <NGO>))を列挙し、概説できる。(B-1-9-*-2) [2]
- B-2 法医学と関連法規
- B-2-1) 死と法
- ①植物状態、脳死、心臓死及び脳死判定を説明できる。(B-2-1-*-1) [1]
- ②異状死・異状死体の取り扱いと死体検案を説明できる。(B-2-1-*-2) [3]
- ③死亡診断書と死体検案書を作成できる。(B-2-1-*-3) [2]
- ④個人識別の方法を説明できる。(B-2-1-*-4) [4]
- ⑤病理解剖、法医解剖(司法解剖、行政解剖、死因・身元調査法解剖、承諾解剖)を説明できる。(B-2-1-*-5) [2]
- B-2-2) 診療情報と諸証明書
- ①診療録(カルテ)に関する基本的な知識(診療録の管理と保存(電子カルテを含む)、診療録の内容、診療情報の開示、プライバシー保護、セキュリティー、問題志向型医療記録<POMR>、主観的所見、客観的所見、評価、計画(subjective, objective, assessment, plan <SOAP>))を説明でき、実際に作成できる。(B-2-2-*-1) [5]
- ②診療に関する諸記録(処方箋、入院診療計画書、検査・画像・手術の記録、退院時要約)を説明できる。(B-2-2-*-2) [5]
- ③診断書、検案書、証明書(診断書、出生証明書、死産証書、死胎検案書、死亡診断書、死体検案書)を説明できる。(B-2-2-*-3) [4]
- ④電子化された診療情報の作成ができ、管理を説明できる。(B-2-2-*-4) [3]
- B-3 医学研究と倫理
- B-3-1) 倫理規範と実践倫理
- ①医学研究と倫理(それぞれの研究に対応した倫理指針と法律)を説明できる。(B-3-1-*-1) [3]
- ②臨床研究、臨床試験、治験と市販後臨床試験の違いを概説できる。(B-3-1-*-2) [3]
- ③臨床試験・治験と倫理性(ヘルシンキ宣言、第Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ相試験、医薬品の臨床試験の実施の基準(Good Clinical Practice <GCP>)、治験審査委員会・倫理審査委員会(institutional review board <IRB>))を説明できる。(B-3-1-*-3) [2]
- ④薬物に関する法令を概説し、医薬品の適正使用に関する事項を列挙できる。(B-3-1-*-4) [1]
- ⑤副作用と有害事象の違い、報告の意義(医薬品・医療機器等安全性情報報告制度等)を説明できる。(B-3-1-*-5) [5]
- B-4 医療に関連のある社会科学領域
- B-4-1) 医師に求められる社会性
- ①医療人類学や医療社会学等の行動科学・社会科学の基本的な視点・方法・理論を概説できる。(B-4-1-*-1) [1]
- ②病気・健康・医療・死をめぐる文化的な多様性を説明できる。(B-4-1-*-2) [2]
- ③自身が所属する文化を相対化することができる。(B-4-1-*-3) [0]
- ④人々の暮らしの現場において病気・健康がどのようにとらえられているかを説明できる。(B-4-1-*-4) [1]
- ⑤人の言動の意味をその人の人生史や社会関係の文脈の中で説明することができる。(B-4-1-*-5) [0]
- ⑥文化・ジェンダーと医療の関係を考えることができる。(B-4-1-*-6) [1]
- ⑦国際保健・医療協力の現場における文化的な摩擦について、文脈に応じた課題を設定して、解決案を提案できる。(B-4-1-*-7) [0]
- ⑧社会をシステムとして捉えることができる。(B-4-1-*-8) [1]
- ⑨病人役割を概説できる。(B-4-1-*-9) [1]
- ⑩対人サービスの困難(バーンアウトリスク)を概説できる。(B-4-1-*-10) [1]
- ⑪経済的側面や制度的側面をふまえた上で、医療現場の実践を評価できる。(B-4-1-*-11) [3]
- ⑫在宅療養と入院または施設入所との関係について総合的な考察ができる。(B-4-1-*-12) [1]
- ⑬多職種の医療・保健・福祉専門職、患者・利用者、その家族、地域の人々など、様々な立場の人が違った視点から医療現場に関わっていることを理解する。(B-4-1-*-13) [3]
- ⑭具体的な臨床事例に文化・社会的課題を見いだすことができる。(B-4-1-*-14) [1]