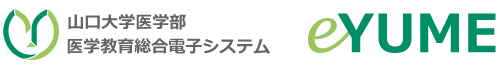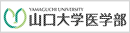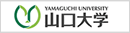ユニット概要
Unit
目標
1.主題
1. 精神症状を呈する様々な精神障害への適切な診断および治療介入を行う能力を身につける。
2. 神経生物学的、心理社会学的な知識を基盤とし、各種精神障害の病態を多面的・総合的に理解する。
2.到達目標
1.患者-医師の良好な信頼関係に基づく精神科面接の基本を説明できる。
2. 患者の心理的および社会的背景を把握し、抱える問題点を抽出・整理できる。
3. 精神科医療の法と倫理について説明できる。
4. 主な精神障害の症候と診断を説明できる。
5. 主な精神障害の治療を概説できる。
6. 中枢神経作用薬の薬理作用を説明できる。
7. コンサルテーション・リエゾン精神医学を説明できる。
3.ねらい(H28コアカリ等対応)
▼ねらい番号を表示
- A-4-2-*-*
- 患者と医師の良好な関係を築くために、患者の個別的背景を理解し、問題点を把握する能力を獲得する。
- A-5-1-*-*
- 医療チームの構成員として、相互の尊重のもとに適切な行動をとるとともに、後輩等に対する指導を行う。
- B-1-5-*-*
- 生活習慣(食生活を含む)とそのリスクについて学ぶ。
- B-1-7-*-*
- 地域医療・地域保健の在り方と現状及び課題を理解し、地域医療に貢献するための能力を獲得する。
- B-1-8-*-*
- 限られた医療資源の有効活用の視点を踏まえ、保健・医療・福祉・介護の制度の内容を学ぶ。
- C-5-*-*-*
- 人の行動と心理を理解するための基礎的な知識と考え方を学ぶ。
- D-2-*-*-*
- 神経系の正常構造と機能を理解し、主な神経系疾患の病因、病態生理、症候、診断と治療を学ぶ。
- D-6-*-*-*
- 呼吸器系の構造と機能を理解し、主な呼吸器疾患の病因、病態生理、症候、診断と治療を学ぶ。
- D-15-*-*-*
- 精神と行動の障害に対して、児童・思春期から老年期のライフステージに応じた病態生理、診断、治療を理解し、良好な患者と医師の信頼関係に基づいた全人的医療を学ぶ。
- E-5-*-*-*
- 中毒と環境要因によって生じる疾患の病態生理を理解し、症候、診断と治療を学ぶ。
- E-7-*-*-*
- 胎児・新生児・乳幼児・小児期から思春期にかけての生理的成長・発達とその異常の特徴及び精神・社会的な問題を理解する。
- E-9-1-*-*
- 個体の死を理解する。
▲ねらい番号を閉じる
4.学修目標(H28コアカリ等対応)
▼コアカリ番号を表示
- A-4-2-*-1
- ①患者と家族の精神的・身体的苦痛に十分配慮できる。
- A-4-2-*-2
- ②患者に分かりやすい言葉で説明できる。
- A-4-2-*-3
- ③患者の心理的及び社会的背景や自立した生活を送るための課題を把握し、抱える問題点を抽出・整理できる。
- A-5-1-*-1
- ①チーム医療の意義を説明できる。
- A-5-1-*-2
- ②医療チームの構成や各構成員(医師、歯科医師、薬剤師、看護師、その他の医療職)の役割分担と連携・責任体制を説明し、チームの一員として参加できる。
- A-5-1-*-4
- ④保健、医療、福祉と介護のチーム連携における医師の役割を説明できる。
- B-1-5-*-5
- ⑤喫煙(状況、有害性、受動喫煙防止、禁煙支援)、飲酒(状況、有害性、アルコール依存症からの回復支援)を説明できる。
- B-1-7-*-3
- ③地域包括ケアシステムの概念を理解し、地域における、保健(母子保健、学校保健、成人・高齢者保健、地域保健、精神保健)・医療・福祉・介護の分野間及び多職種間(行政を含む)の連携の必要性を説明できる。
- B-1-7-*-5
- ⑤地域における救急医療、在宅医療及び離島・へき地医療の体制を説明できる。
- B-1-8-*-13
- ⑬障害者福祉・精神保健医療福祉の現状と制度を説明できる。
- C-5-6-*-1
- ①パーソナリティの類型と特性を概説できる。
- C-5-6-*-2
- ②パーソナリティの形成を概説できる。
- D-2-1-4-2
- ②大脳皮質の機能局在(運動野・感覚野・言語野)を説明できる。
- D-2-4-7-1
- ①てんかんの分類、診断と治療を説明できる。
- D-6-4-6-1
- ①過換気症候群を概説できる。
- D-15-1-*-1
- ①患者-医師の良好な信頼関係に基づく精神科面接の基本を説明できる。
- D-15-1-*-2
- ②精神科診断分類法を説明できる。
- D-15-1-*-3
- ③精神科医療の法と倫理に関する必須項目(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、心神喪失者等医療観察法、インフォームド・コンセント)を説明できる。
- D-15-1-*-4
- ④コンサルテーション・リエゾン精神医学を説明できる。
- D-15-1-*-5
- ⑤心理学的検査法(質問紙法、Rorschach テスト、簡易精神症状評価尺度(Brief Psychiatric Rating Scale <BPRS>)、Hamilton うつ病評価尺度、Beck のうつ病自己評価尺度、状態特性不安検査(State-Trait Anxiety Inventory <STAI>)、Mini-Mental State Examination <MMSE>、改訂長谷川式簡易知能評価スケール等)の種類と概要を説明できる。
- D-15-2-*-1
- ①不安・躁うつをきたす精神障害を列挙し、その鑑別診断を説明できる。
- D-15-2-*-2
- ②意識障害、不眠、幻覚・妄想をきたす精神障害を列挙し、その鑑別診断を説明できる。
- D-15-3-*-1
- ①症状精神病の概念と診断を概説できる。
- D-15-3-*-3
- ③薬物使用に関連する精神障害やアルコール、ギャンブル等への依存症の病態と症候を説明できる。
- D-15-3-*-4
- ④統合失調症の症候と診断、救急治療を説明できる。
- D-15-3-*-5
- ⑤うつ病の症候と診断を説明できる。
- D-15-3-*-6
- ⑥双極性障害(躁うつ病)の症候と診断を説明できる。
- D-15-3-*-7
- ⑦不安障害群と心的外傷及びストレス因関連障害群の症候と診断を説明できる。
- D-15-3-*-8
- ⑧身体症状症及び関連症群、食行動障害及び摂食障害群の症候と診断を説明できる。
- D-15-3-*-9
- ⑨解離性障害群の症候、診断と治療を説明できる。
- D-15-3-*-10
- ⑩パーソナリティ障害群を概説できる。
- D-15-3-*-11
- ⑪知的能力障害群と自閉症スペクトラム障害(autism spectrum disorder <ASD>)を概説できる。
- D-15-3-*-12
- ⑫注意欠如・多動障害(attention deficit / hyperactivity disorder <ADHD>)と運動障害群を概説できる。
- E-5-3-1-5
- ⑤アルコール、覚醒剤・麻薬・大麻などの乱用薬物による中毒を説明できる。
- E-7-3-*-6
- ⑥児童虐待を概説できる。
- E-7-3-*-8
- ⑧神経発達障害群(自閉症スペクトラム障害<ASD>、注意欠如・多動障害<ADHD>、限局性学習障害、チック障害群)を列挙できる。
- E-7-4-*-2
- ②思春期と関連した精神保健上の問題を列挙できる。
- E-9-1-*-6
- ⑥死に至る身体と心の過程を説明できる。その個別性にも共感配慮できる。
- E-9-1-*-7
- ⑦人生の最終段階における医療(エンド・オブ・ライフ・ケア)での患者とのコミュニケーション、頻度の高い苦痛とその対処法・ケアを説明できる。
- E-9-1-*-9
- ⑨人生の最終段階における医療(エンド・オブ・ライフ・ケア)での本人の意思決定、事前指示、延命治療、Do not attempt resuscitation <DNAR>、尊厳死と安楽死、治療の中止と差し控えの概念を説明できる。
- E-9-1-*-10
- ⑩患者の死後の家族ケア(悲嘆のケア(グリーフケア))を説明できる。
- F-3-5-1-1
- ①患者の立場を尊重し、信頼を得ることができる。
- Y-6-5-*-21
- 21)乱用薬物について、薬理作用や生体への影響を説明できる。
- Y-15-3-*-1
- 1)精神疾患の基本的な脳病態生理について説明できる。
- Y-15-3-*-2
- 2)精神医療保健福祉のシステムを説明できる。
▲コアカリ番号を閉じる
5.旧一般学習目標(GIO)
▼旧一般学習目標(GIO)を表示
精神症状を呈する様々な精神障害への適切な診断および治療介入を行う能力を得るために、神経生物学的、心理社会学的な知識を基盤とした多面的・総合的な病態の理解を身につけ、各種精神障害の診断・治療法を修得する。
▲旧一般学習目標(GIO)を閉じる
方略(LS)
1.ユニット構成
日付昇順で表示
試験
| 項目 |
年月日曜日時限 |
内容 |
担当者 |
場所 |
コアカリ番号 |
|
2018年5月21日(月)
3・4時限(4年)
|
筆記試験 |
原田健一郎 |
第3講義室 |
|
講義
| 授業ID |
回 |
年月日曜日時限 |
講義内容 |
担当者 |
場所 |
コアカリ番号 |
| k0415660900 |
14 |
2018年5月16日(水)
7・8時限(4年)
|
緩和ケア
|
松原敏郎 |
第2講義室 |
D-15-1-*-1,D-15-1-*-3,E-9-1-*-6,E-9-1-*-7,E-9-1-*-9,E-9-1-*-10 |
| k0415661100 |
13 |
2018年5月16日(水)
5・6時限(4年)
|
パーソナリティ障害
|
松原敏郎 |
第2講義室 |
D-15-3-*-10,C-5-6-*-1,C-5-6-*-2,B-1-5-*-5 |
| k0415661500 |
12 |
2018年5月15日(火)
7・8時限(4年)
|
精神薬理学
|
松尾幸治 |
第2講義室 |
|
| k0415660200 |
11 |
2018年5月15日(火)
5・6時限(4年)
|
法と精神医学
|
河野通英 |
第2講義室 |
D-15-1-*-3,Y-15-3-*-2,B-1-8-*-13 |
| k0415660700 |
10 |
2018年5月14日(月)
5・6時限(4年)
|
神経症性障害
|
山形弘隆 |
第2講義室 |
A-4-2-*-2,D-6-4-6-1,D-15-1-*-1,D-15-1-*-5,D-15-3-*-7,D-15-3-*-8,D-15-3-*-9 |
| k0415661400 |
9 |
2018年5月11日(金)
3・4時限(4年)
|
精神科救急と司法精神医学
|
兼行浩史 |
第2講義室 |
B-1-7-*-3,D-15-1-*-3,B-1-7-*-5 |
| k0415660400 |
8 |
2018年5月11日(金)
1・2時限(4年)
|
依存症
|
佐々木順 |
第2講義室 |
D-15-3-*-3,E-5-3-1-5,Y-6-5-*-21,B-1-5-*-5 |
| k0415661000 |
7 |
2018年5月10日(木)
3・4時限(4年)
|
精神科リハビリテーション
|
樋口文宏 |
第2講義室 |
B-1-7-*-3,A-5-1-*-1,A-5-1-*-2,A-5-1-*-4 |
| k0415660500 |
6 |
2018年5月10日(木)
1・2時限(4年)
|
統合失調症
|
樋口文宏 |
第2講義室 |
D-15-2-*-2,D-15-3-*-4 |
| k0415661300 |
5 |
2018年5月9日(水)
3・4時限(4年)
|
心理学からの精神疾患へのアプローチ
|
橋本亜希子 |
第2講義室 |
D-15-1-*-1,D-15-1-*-5,F-3-5-1-1 |
| k0415660600 |
4 |
2018年5月9日(水)
1・2時限(4年)
|
器質性・症状性精神障害、リエゾン精神医学
|
關友恵 |
第2講義室 |
D-2-4-7-1,D-15-2-*-1,D-15-2-*-2,D-15-3-*-1,A-5-1-*-1,D-15-1-*-4 |
| k0415660800 |
3 |
2018年5月7日(月)
7・8時限(4年)
|
気分障害
|
山形弘隆 |
第2講義室 |
D-15-2-*-1,D-15-3-*-5,D-15-3-*-6 |
| k0415661200 |
2 |
2018年5月2日(水)
3・4時限(4年)
|
児童・思春期の精神医学
|
原田健一郎 |
第2講義室 |
D-15-3-*-11,D-15-3-*-12,E-7-3-*-6,E-7-3-*-8,E-7-4-*-2 |
| k0415660100 |
1 |
2018年5月2日(水)
1・2時限(4年)
|
精神医学総論(診断学)
|
中川伸 |
第2講義室 |
A-4-2-*-1,A-4-2-*-3,D-15-1-*-1,D-15-1-*-2,D-2-1-4-2,Y-15-3-*-1 |
2.テキスト
| 必要度 |
書名 |
著者・監修者・訳者 |
出版社 |
出版年 |
本体価格 |
| 1 |
現代臨床精神医学(改訂12版) |
大熊輝雄 著 |
金原出版 |
2013 |
8085 |
| 1 |
標準精神医学(第6版) |
野村総一郎、樋口輝彦 著 |
医学書院 |
2015 |
6825 |
| 2 |
カプラン 臨床精神医学テキスト(Synopsis of Psychiatry)(第3版) |
カプラン 著, 井上令一, 四宮滋子 監訳 |
メディカル・サイエンス・インターナショナル |
2016 |
21600 |
| 3 |
精神医学事典(新版) |
加藤正明 他編 |
弘文堂 |
1993 |
24466 |
1 必携(授業に必ず持参するもの)
2 推奨(学習する際に読むことを強く勧めるもの)
3 参考(参考書として適切なもの)
3.教育方法等の特記事項
総論から各論まで流れが一貫した講義形式とする。病態などの理解を進めるために積極的にビデオなどを用いる。また,講義では思考方法を重視し,知識の主体的学修を促す。症例呈示などを通して課題解決型学修を試みる。
評価方法
ユニットの最終日に,ユニット全内容についての筆記試験を行う。筆記試験が医師国家試験に準じた形式を用いる。ユニット進行中にも適宜小テストやレポートが課されることがある。成績評価は,これらの試験やレポート,授業への参加態度を総合的に判断する。
注意点(再試等)
ユニット責任者の判断により,再試を行う場合がある。