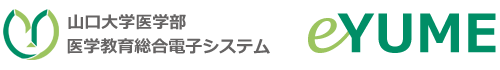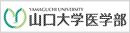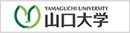検索
Search
- A 医師として求められる基本的な資質・能力
- A-1 プロフェッショナリズム
- A-1-1) 医の倫理と生命倫理
- ①医学・医療の歴史的な流れとその意味を概説できる。(A-1-1-*-1) [12]
- ②臨床倫理や生と死に関わる倫理的問題を概説できる。(A-1-1-*-2) [12]
- ③ヒポクラテスの誓い、ジュネーブ宣言、医師の職業倫理指針、医師憲章等医療の倫理に関する規範を概説できる。(A-1-1-*-3) [8]
- A-1-2) 患者中心の視点
- ①リスボン宣言等に示された患者の基本的権利を説明できる。(A-1-2-*-1) [15]
- ②患者の自己決定権の意義を説明できる。(A-1-2-*-2) [17]
- ③選択肢が多様な場合でも適切に説明を行い患者の価値観を理解して、患者の自己決定を支援する。(A-1-2-*-3) [6]
- ④インフォームド・コンセントとインフォームド・アセントの意義と必要性を説明できる。(A-1-2-*-4) [11]
- A-1-3) 医師としての責務と裁量権
- ①診療参加型臨床実習において患者やその家族と信頼関係を築くことができる。(A-1-3-*-1) [8]
- ②患者やその家族のもつ価値観や社会的背景が多様であり得ることを認識し、そのいずれにも柔軟に対応できる。(A-1-3-*-2) [13]
- ③医師が患者に最も適した医療を勧めなければならない理由を説明できる。(A-1-3-*-3) [13]
- ④医師には能力と環境により診断と治療の限界があることを説明できる。(A-1-3-*-4) [13]
- ⑤医師の法的義務を列挙し、例示できる。(A-1-3-*-5) [9]
- A-2 医学知識と問題対応能力
- A-2-1) 課題探求・解決能力
- ①必要な課題を自ら発見できる。(A-2-1-*-1) [31]
- ②自分に必要な課題を、重要性・必要性に照らして順位付けできる。(A-2-1-*-2) [31]
- ③課題を解決する具体的な方法を発見し、課題を解決できる。(A-2-1-*-3) [42]
- ④課題の解決に当たり、他の学修者や教員と協力してよりよい解決方法を見出すことができる。(A-2-1-*-4) [55]
- ⑤適切な自己評価ができ、改善のための具体的方策を立てることができる。(A-2-1-*-5) [31]
- A-2-2) 学修の在り方
- ①講義、国内外の教科書・論文、検索情報等の内容について、重要事項や問題点を抽出できる。(A-2-2-*-1) [60]
- ②得られた情報を統合し、客観的・批判的に整理して自分の考えを分かりやすく表現できる。(A-2-2-*-2) [51]
- ③実験・実習の内容を決められた様式に従って文書と口頭で発表できる。(A-2-2-*-3) [41]
- ④後輩等への適切な指導が実践できる。(A-2-2-*-4) [2]
- ⑤各自の興味に応じて選択制カリキュラム(医学研究等)に参加する。(A-2-2-*-5) [1]
- A-3 診療技能と患者ケア
- A-3-1) 全人的実践的能力
- ①病歴(主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活歴、社会歴・職業歴、システムレビュー等)を適切に聴取するとともに患者との良好な関係を構築し、必要に応じて患者教育を行える。(A-3-1-*-1) [4]
- ②網羅的に系統立てて適切な順序で効率的な身体診察を行える。異常所見を認識・記録し、適切な鑑別診断が行える。(A-3-1-*-2) [3]
- ③基本的な臨床技能(適応、実施方法、合併症、注意点)を理解し、適切な態度で診断や治療を行える。(A-3-1-*-3) [3]
- ④診療録(カルテ)についての基本的な知識を修得し、問題志向型医療記録(problem-oriented medical record<POMR>)形式で診療録を作成し、必要に応じて医療文書を作成できる。(A-3-1-*-4) [2]
- ⑤患者の病状(症状、身体所見、検査所見等)、プロブレムリスト、鑑別診断、臨床経過、治療法の要点を提示し、医療チーム構成員と意見交換ができる。(A-3-1-*-5) [2]
- ⑥緊急を要する病態や疾患・外傷の基本的知識を説明できる。診療チームの一員として救急医療に参画できる。(A-3-1-*-6) [2]
- ⑦慢性疾患や慢性疼痛の病態、経過、治療を説明できる。医療を提供する場や制度に応じて、診療チームの一員として慢性期医療に参画できる。(A-3-1-*-7) [2]
- ⑧患者の苦痛や不安感に配慮しながら、就学・就労、育児・介護等との両立支援を含め患者と家族に対して誠実で適切な支援を行える。(A-3-1-*-8) [1]
- A-4 コミュニケーション能力
- A-4-1) コミュニケーション
- ①コミュニケーションの方法と技能(言語的と非言語的)を説明し、コミュニケーションが態度あるいは行動に及ぼす影響を概説できる。(A-4-1-*-1) [10]
- ②コミュニケーションを通じて良好な人間関係を築くことができる。(A-4-1-*-2) [57]
- ③患者・家族の話を傾聴し、共感することができる。(A-4-1-*-3) [7]
- A-4-2) 患者と医師の関係
- ①患者と家族の精神的・身体的苦痛に十分配慮できる。(A-4-2-*-1) [13]
- ②患者に分かりやすい言葉で説明できる。(A-4-2-*-2) [14]
- ③患者の心理的及び社会的背景や自立した生活を送るための課題を把握し、抱える問題点を抽出・整理できる。(A-4-2-*-3) [18]
- ④医療行為が患者と医師の契約的な信頼関係に基づいていることを説明できる。(A-4-2-*-4) [14]
- ⑤患者の要望(診察・転医・紹介)への対処の仕方を説明できる。(A-4-2-*-5) [11]
- ⑥患者のプライバシーに配慮できる。(A-4-2-*-6) [10]
- ⑦患者情報の守秘義務と患者等への情報提供の重要性を理解し、適切な取扱いができる。(A-4-2-*-7) [11]
- A-5 チーム医療の実践
- A-5-1) 患者中心のチーム医療
- ①チーム医療の意義を説明できる。(A-5-1-*-1) [9]
- ②医療チームの構成や各構成員(医師、歯科医師、薬剤師、看護師、その他の医療職)の役割分担と連携・責任体制を説明し、チームの一員として参加できる。(A-5-1-*-2) [29]
- ③自分の能力の限界を認識し、必要に応じて他の医療従事者に援助を求めることができる。(A-5-1-*-3) [29]
- ④保健、医療、福祉と介護のチーム連携における医師の役割を説明できる。(A-5-1-*-4) [11]
- A-6 医療の質と安全の管理
- A-6-1) 安全性の確保
- ①実際の医療には、多職種が多段階の医療業務内容に関与していることを具体的に説明できる。(A-6-1-*-1) [17]
- ②医療上の事故等を防止するためには、個人の注意(ヒューマンエラーの防止)はもとより、組織的なリスク管理(制度・組織エラーの防止)が重要であることを説明できる。(A-6-1-*-2) [15]
- ③医療現場における報告・連絡・相談と記録の重要性や、診療録(カルテ)改竄の違法性を説明できる。(A-6-1-*-3) [15]
- ④医療の安全性に関する情報(薬剤等の副作用、薬害、医療過誤(事例や経緯を含む)、やってはいけないこと、優れた取組事例等)を共有し、事後に役立てるための分析の重要性を説明できる。(A-6-1-*-4) [14]
- ⑤医療の安全性確保のため、職種・段階に応じた能力向上の必要性を説明できる。(A-6-1-*-5) [8]
- ⑥医療機関における医療安全管理体制の在り方(事故報告書、インシデントレポート、医療事故防止マニュアル、医療廃棄物処理、医療安全管理者(リスクマネージャー)、安全管理委員会、事故調査委員会、医療事故調査制度、産科医療補償制度)を概説できる。(A-6-1-*-6) [11]
- ⑦医療関連感染症の原因及び回避する方法(院内感染対策委員会、院内感染サーベイランス、院内感染対策チーム(infection control team <ICT>)、感染対策マニュアル等)を概説できる。(A-6-1-*-7) [3]
- ⑧真摯に疑義に応じることができる。(A-6-1-*-8) [5]
- A-6-2) 医療上の事故等への対処と予防
- ①医療上の事故等(インシデントを含む)と合併症の違いを説明できる。(A-6-2-*-1) [12]
- ②医療上の事故等(インシデントを含む)が発生したときの緊急処置や記録、報告を説明し、実践できる。(A-6-2-*-2) [12]
- ③医療過誤に関連した刑事・民事責任や医師法に基づく行政処分を説明できる。(A-6-2-*-3) [11]
- ④基本的予防策(ダブルチェック、チェックリスト法、薬品名称の改善、フェイルセイフ・フールプルーフの考え方等)を概説し、指導医の指導の下に実践できる。(A-6-2-*-4) [5]
- A-6-3) 医療従事者の健康と安全
- ①医療従事者の健康管理(予防接種を含む)の重要性を説明できる。(A-6-3-*-1) [5]
- ②標準予防策(standard precautions)の必要性を説明し、実行できる。(A-6-3-*-2) [5]
- ③患者隔離の必要な場合を説明できる。(A-6-3-*-3) [5]
- ④針刺し事故(針刺切創)等に遭遇した際の対処の仕方を説明できる。(A-6-3-*-4) [5]
- ⑤医療現場における労働環境の改善の必要性を説明できる。(A-6-3-*-5) [3]
- A-7 社会における医療の実践
- A-7-1) 地域医療への貢献
- ①地域社会(離島・へき地を含む)における医療の状況、医師の偏在(地域、診療科及び臨床・非臨床)の現状を概説できる。(A-7-1-*-1) [1]
- ②医療計画(医療圏、基準病床数、地域医療支援病院、病診連携、病病連携、病院・診療所・薬局の連携等)及び地域医療構想を説明できる。(A-7-1-*-2) [1]
- ③地域包括ケアシステムの概念を理解し、地域における保健(母子保健、学校保健、成人・高齢者保健、地域保健、精神保健)・医療・福祉・介護の分野間及び多職種間(行政を含む)の連携の必要性を説明できる。(A-7-1-*-3) [1]
- ④かかりつけ医等の役割や地域医療の基盤となるプライマリ・ケアの必要性を理解し、実践に必要な能力を獲得する。(A-7-1-*-4) [1]
- ⑤地域における救急医療、在宅医療及び離島・へき地医療の体制を説明できる。(A-7-1-*-5) [1]
- ⑥災害医療(災害時保健医療、医療救護班、災害派遣医療チーム(DisasterMedical Assistance Team<DMAT>)、災害派遣精神医療チーム(Disaster Psychiatric Assistance Team <DPAT>)、日本医師会災害医療チーム(JapanMedical Association Team <JMAT>)、災害拠点病院、トリアージ等)を説明できる。(A-7-1-*-6) [1]
- ⑦地域医療に積極的に参加・貢献する。(A-7-1-*-7) [1]
- A-7-2) 国際医療への貢献
- ①患者の文化的背景を尊重し、英語をはじめとした異なる言語に対応することができる。(A-7-2-*-1) [0]
- ②地域医療の中での国際化を把握し、価値観の多様性を尊重した医療の実践に配慮することができる。(A-7-2-*-2) [1]
- ③保健、医療に関する国際的課題を理解し、説明できる。(A-7-2-*-3) [1]
- ④日本の医療の特徴を理解し、国際社会への貢献の意義を理解している。(A-7-2-*-4) [1]
- ⑤医療に関わる国際協力の重要性を理解し、仕組みを説明できる。(A-7-2-*-5) [1]
- A-8 科学的探究
- A-8-1) 医学研究への志向の涵養
- ①研究は、医学・医療の発展や患者の利益の増進を目的として行われるべきことを説明できる。(A-8-1-*-1) [3]
- ②生命科学の講義・実習で得た知識を基に、診療で経験した病態の解析ができる。(A-8-1-*-2) [5]
- ③患者や疾患の分析を基に、教科書・論文等から最新の情報を検索・整理統合し、疾患の理解・診断・治療の深化につなげることができる。(A-8-1-*-3) [5]
- ④抽出した医学・医療情報から新たな仮説を設定し、解決に向けて科学的研究(臨床研究、疫学研究、生命科学研究等)に参加することができる。(A-8-1-*-4) [3]
- A-9 生涯にわたって共に学ぶ姿勢
- A-9-1) 生涯学習への準備
- ①生涯学習の重要性を説明できる。(A-9-1-*-1) [10]
- ②生涯にわたる継続的学習に必要な情報を収集できる。(A-9-1-*-2) [6]
- ③キャリア開発能力を獲得する。(A-9-1-*-3) [3]
- ④キャリアステージにより求められる能力に異なるニーズがあることを理解する。(A-9-1-*-4) [3]
- ⑤臨床実習で経験したことを省察し、自己の課題を明確にする。(A-9-1-*-5) [2]